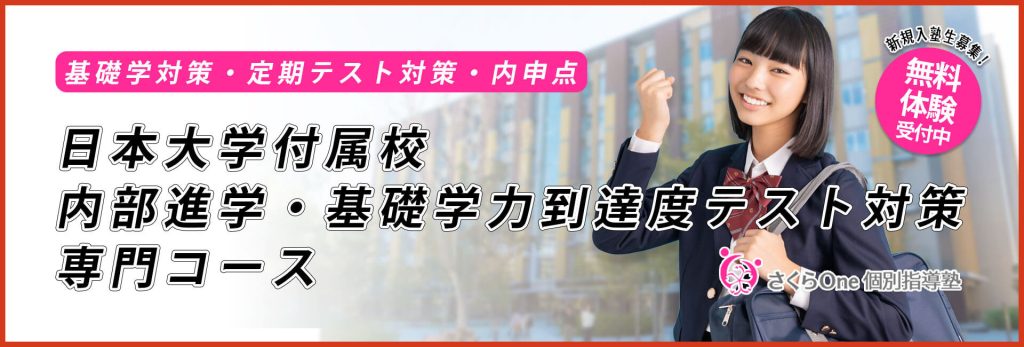日大基礎学力到達度テスト【数学】出題傾向と対策
はじめに
日本大学付属高等学校等で実施される基礎学力到達度テスト(基礎到達テスト)は、附属校の内部進学を目指す生徒にとって非常に重要な試験です。今回は「基礎学力到達度テスト」の中でも、多くの受験生が気になる数学の傾向と対策について、文系・理系の視点から解説していきます。
基礎学力到達度テストとは?
基礎学力到達度テストは、日本大学の付属高校で行われる統一試験で、主に内部進学のための基準として活用されます。高校2年生(2年次)と高校3年生(3年次)に実施され、試験結果は進学判定や進路選択に大きく影響します。
数学の出題範囲と内容
2年4月(文系・理系共通)
| 範囲 | 内容 |
|---|---|
| 数Ⅰ・A | すべての範囲 |
3年4月(文系・理系共通)
| 範囲 | 内容 |
|---|---|
| 数Ⅱ | すべての範囲 |
| 数B | *¹数列、*²統計 |
| 数C | *³ベクトル |
*¹数列、*²統計、*³ベクトルの3つから2つを選択
3年9月(文系)
| 範囲 | 内容 |
|---|---|
| 数Ⅰ・A | すべての範囲 |
| 数Ⅱ | すべての範囲 |
| 数B | *¹数列、*²統計 |
| 数C | *³ベクトル |
*¹数列、*²統計、*³ベクトルの3つから2つを選択
3年9月(理系)
| 範囲 | 内容 |
|---|---|
| 数Ⅰ・A | すべての範囲 |
| 数Ⅱ | すべての範囲 |
| 数B | 数列、*¹統計 |
| 数C | ベクトル、*²平面上の曲線・複素数平面 |
| 数Ⅲ | 極限、*³微分 |
*¹統計、*²平面上の曲線・複素数平面、*³微分の3つから1つを選択
出題範囲
基礎学力テストの数学では、数I・A、数Ⅱ・Bが中心となっています。2年次は比較的基礎的な内容が多く、3年次は応用力が求められます。
出題内容の例:
- 二次関数
- データの分析
- 図形と計量(三角比)
- 場合の数と確率
- 整数の性質(約数、公倍数など)
理系・文系での数学の違い
文系
文系でも数学は必須科目として課されることが増えてきています。しかし出題される内容はやや基礎的で、計算力やパターン問題の理解が重視されがちです。
文系のポイント:
- 数I・A、数Ⅱの基礎をしっかり固める
- 数B・C(整列・統計・ベクトルの中から2分野選択)の選択分野を集中的に
- データ分析や割合、グラフなどの実用数学を重点的に
- 式変形や因数分解などのスピード強化
理系
理系での数学は非常に重要です。基礎テストでも高得点を取っておきたい科目ですし、試験の難易度も文系よりやや応用寄りになることが多いです。
理系で問われる分野:
- 数Ⅰ・Aと数Ⅱは全体的に対応できるように
- 数B(数列)
- 数C(ベクトル)
- 数Ⅲ(極限)
- 数B・C・Ⅲ(統計、平面上の曲線・複素数平面、微分)の選択分野を集中的に
- 数学的な読解力・論理的推論
2年生と3年生で出題の難易度や傾向が異なりますので、詳しく見ていきましょう。
2年次:試験範囲と形式、内容と対策
1年生までに学ぶ範囲がベースなので、比較的基礎的な内容が多いです。
①範囲
2年次では、数I・Aすべてが含まれるのが特徴です。
- 数I:二次関数、データの分析、図形と計量
- 数A:場合の数・確率、整数の性質、図形の性質
②形式
- 試験時間:60分
- 配点:100点満点
- 出題形式:マークシート方式中心
- 論理力や読解力が問われる
- 問題数はやや多めで、時間との勝負になることも
③内容
- 「グラフ」「統計資料」「表」などの読み取り問題も出題
- 設定に沿って数理的に考える力を試す問題も多い
④対策
- 過去問や模試で時間配分の練習
3年次:試験範囲と形式、内容と対策
3年次では4月と9月に試験があり、2年次よりも難易度が高く、応用力が求められます。
3年4月
文系・理系共通で出題されます。
①範囲
数II・B・Cに関する出題が予想され、数B・Cについては2分野を選択する方式になります。
- 数II:式と証明、三角関数、指数・対数、図形と方程式、微分積分(基礎)
- 数B:*¹数列(和の公式、漸化式)、*²統計
- 数C:*³ベクトル(内積・座標)
*¹数列、*²統計、*³ベクトルから2分野を選択
②形式
- 試験時間:60分
- 配点:100点満点
- 出題形式:マーク式中心だが、記述形式(導出や説明)も一部導入されることあり
- 問題数は少なめでも、1問ごとの情報量と処理量が多い
- 数学的思考力を問う記述問題が出る
③内容
- 完全な応用問題寄り
- 現実的な場面設定や、抽象的な数理構造の理解を要する問題が増加
- 論証・比較・証明型の問題が出題されることもある
④対策
- 数II・Bの発展問題に取り組む(教科書+青チャート・標準問題集など)
- 記述力・説明力を鍛える(解法だけでなく考え方を言語化)
- 数学的読解力・構造把握力を養う(文章題・図形・関数の絡み)
3年9月(文系)
4月の範囲に数Ⅰ・Aが追加され、数B・Cについては2分野を選択する方式になります。
①範囲
- 数Ⅰ・A:すべての範囲
- 数Ⅱ:すべての範囲
- 数B:*¹整列、*²統計
- 数C:*³ベクトル
*¹整列、*²統計、*³ベクトルから2分野を選択
3年次9月(理系)
4月の範囲に数Ⅰ・A、数Ⅲ・Cが追加され、3分野から1分野を選択する方式になります。
①範囲
- 数Ⅰ・A:すべての範囲
- 数Ⅱ:すべての範囲
- 数B:数列、*¹統計
- 数C:ベクトル、*²平面上の曲線・複素数平面
- 数Ⅲ:極限、*³微分
*¹統計、*²平面上の曲線・複素数平面、*³微分から1分野選択
過去問の活用法
基礎学力到達度テストの過去問を活用することは、最も効率的な対策のひとつです。過去5年間の出題傾向を分析し、頻出テーマを重点的に学習しましょう。
おすすめの教材
- 『日本大学付属高等学校等 基礎学力到達度テスト 問題と詳解 数学 2025年度版』(清水書院)
まとめ
| 年次 | 文系 | 理系 |
|---|---|---|
| 2年次 | 数I・Aの復習+数IIの基本 | 数I・A+数II・Bまでしっかり対応 |
| 3年次 | 数II・Bの典型問題が中心 | 数IIIの導入含め、本格的な応用力が必要 |
| 共通 | 基礎+思考力+読解力 | 基礎+思考力+論理力+応用力 |
基礎学力到達度テストは、単に“基礎”という名前がついているだけでなく、基礎+論理力=得点源という構成になっています。
理系はもちろん、文系の方にとっても「数学ができるかどうか」で合否が大きく左右される場面があります。
基礎学力到達度テストの数学は、計画的な学習と正しい対策で得点を伸ばすことができます! しっかり準備して、内部進学を確実なものにしましょう。
弊社さくらOne個別指導塾では、日大付属校内部進学の専門コースを開講し、100人以上(2023年度)の生徒様が社会人プロ講師の完全マンツーマンで日本大学への内部進学対策を行っております。
日本大学への内部進学対策をお考えの方は、無料体験授業も行っているさくらOne個別指導塾をご検討ください。