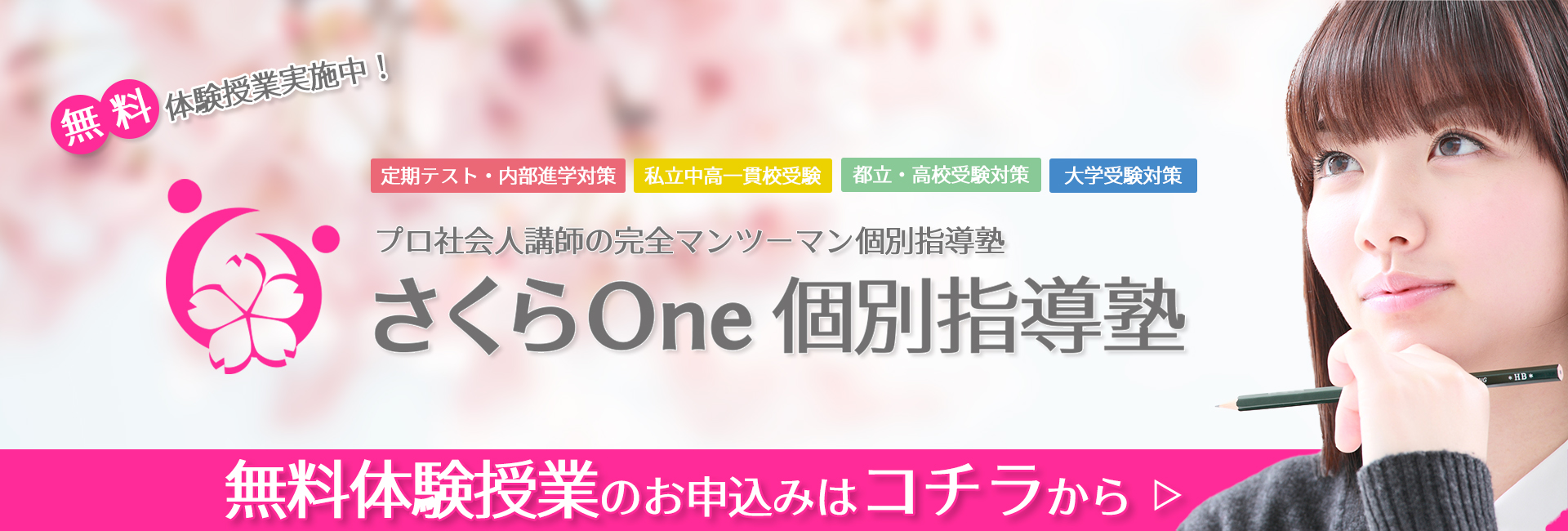【英検準2級】合格するための完全解説ガイド

英検準2級は、高校中級レベルの英語力が問われる試験です。
最近では英語教育の早期化に伴い、中学生のうちに挑戦する受験者が増えています。
本記事では、英検準2級の試験概要や最新の出題傾向、効果的な学習計画について解説します。
2025年度の準2級に関する変更点
試験形式リニューアルと新設級導入
2024年度第1回検定から英検3級以上の級で問題形式がリニューアルされ、準2級でも筆記試験の出題数削減とライティング問題増加が行われました。
具体的には従来1題だったライティングが2題(意見論述+Eメール英文返信)に増え、これに伴い一次試験の筆記時間が75分から80分に延長されています。
一方、配点に関しては各技能の満点スコア(リーディング・リスニング・ライティング各600点満点)や合格基準スコアに変更はありません。
準2級プラスとは
2025年度からは、準2級と2級の間に新たな級「準2級プラス」が導入されました。
準2級プラスは高校上級レベルを対象とした級で、従来準2級から2級へのレベル差が大きかったことへの対策として新設されたものです。
ただし準2級そのものの難易度や出題範囲に大きな変更はなく、検定料も他の級は据え置かれています。
変更点のポイント
ライティングにEメール形式の課題を追加したり、新たな級でステップを細分化したりすることで、受験者の努力がより適切に評価され、次の学習目標が立てやすくなるとされています。
筆記試験(リーディング&ライティング)
準2級一次試験の筆記は80分でリーディングとライティングを測定します。
リーディング問題数はリニューアル後37問→29問に減少しました。
内容は、短文穴埋め選択(語句・熟語問題、15問)、会話文の空所補充(5問)、長文の語句空所補充(2問)、そして長文読解(内容一致選択、7問)で構成されます。
長文読解ではEメールや説明文など実用的な文章を読み、その内容に関する設問に答えます。
ライティングは2題で、まず与えられた設定に対する英文Eメールの返信作成(1題)と、身近なテーマについて自分の意見を英語で記述する作文(1題)です。
Eメール問題は差出人の英文メールを読んだうえで返信文を書く形式、英作文問題は質問文に対し自分の考えを50~60語程度で論述する形式となっており、実生活での通信能力と論述力の両方を見る出題になっています。
筆記全体として、学校生活や日常場面から社会・文化に関する内容まで幅広い題材が扱われます。
語彙レベルは中学卒業程度(約2,200~2,500語)にプラスして高校基礎レベルの単語を含む計3,500~4,000語程度が目安とされています。
リスニング試験
リスニングは約25分間で全30問(3部構成)です。
第1部は対話の応答選択10問で、短い会話の最後の発話に対する適切な応答を選ぶ問題。
第2部は会話内容の理解10問で、やや長めの対話文を聞き内容に関する質問に答える問題。
第3部は文章内容の理解10問で、ナレーションやアナウンスなど短い英文を聞きその内容について問う問題です。
放送は全問1回読みで、設問の場面設定は「家庭、学校、職場、地域の公共施設、電話やアナウンス」といった状況。
話題は「学校、趣味、旅行、買い物、スポーツ、音楽、天気、道案内、海外の文化、環境問題」など多岐にわたります。
近年の傾向として、日常生活の会話表現や意図を問う問題が多く、登場人物の心情推測や要点把握が求められる傾向です。
スピーキング試験(二次面接)
準2級の二次試験は面接官と1対1で行われ、約6分間の英語面接でスピーキング力を測ります。
面接ではまず英文音読を行い、続いてその文章内容についての質問が1問出ます。
次にイラスト描写が2問あり、カードに描かれたイラストを見て「人物の行動を英文で説明する」質問と、「状況・理由を説明する」質問に答えます。
さらに、カードの話題に関連した受験者自身の意見を問う質問が1問、それとは別に日常生活に関する簡単な質問が1問出されます。
合計すると音読+質問5問という構成です。
質問内容は身近な話題について自分の経験や考えを述べるものが多く、例えば過去のトピック例では「ホームシアターについてどう思うか」「地元でボランティアガイドをすることについて意見は?」など高校生の日常や関心に関連するテーマが扱われています。
面接では内容の適切さだけでなく、発音や語彙・文法の正確さ、回答の情報量、そして積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度も評価されます。
傾向として、質問に対して自分なりの考えを英語で説明する力が重視されており、単にYes/Noで答えるのではなく理由を添えて話すことが求められます。
面接委員は優しくリードしてくれますが、緊張に負けず積極的に答える姿勢が高評価につながります。
CSEスコアによる合否判定
英検準2級では、一次試験・二次試験ともに英検CSEスコア(Common Scale for English)によって合否が判定されます。
各技能(Reading, Listening, Writing, Speaking)の満点スコアは各600点と定められており、一次試験(R/L/W合計1800点)と二次試験(S 600点)の合計で満点2400点となります。
一次試験に合格するには、このCSEスコアで約1322点以上を取る必要があります。
1322点は満点(1800点)の約73%に相当し、配点上はだいたい6~7割正答できれば合格ラインと言えます。
ただし実際の合格点は毎回の試験問題の難易度に応じて調整されており、正答率が同じでも回によってCSEスコア換算値が異なるため、「○問正解すれば必ず合格」とは断言できません。
英検協会は2016年以降、各級の合格率を公表していないため正確なラインは受験後のスコア報告で確認する形になりますが、過去の統計上は正答率おおむね60~65%がボーダーと推測されています。
受験者層と想定される英語力の目安
対象レベル
英検協会が示す準2級の難易度目安は「高校中級程度」です。
高校2年生相当の英語力とも言われ、高校英語の基本文法・語法が概ね身についており、日常的な話題であれば平易な英語でコミュニケーションが取れるレベルです。
具体的には中学校卒業レベルの語彙・表現に加え、高校初級~中級の語彙や表現力が求められます。
文章の大意や要点を把握し、自分の意見を簡単な英文で述べることができる力が目標となります。
受験者の年齢層
準2級は従来、高校生が多く受験する級でしたが、近年では中学生で挑戦する受験者も増加しています。
英語教育の早期化により、中学在学中に準2級合格を目指す例も珍しくなくなりました。
実際、「高校中級程度」の試験である準2級に中学3年生で合格するケースも増えており、それを英語力のアピールや高校受験での評価材料にしようという動きも見られます。
ただし学校の英語授業範囲を超える単語・表現が出題されるため、中学生には難易度が高く感じられるのも事実です。
協会も公式に「英検は小学生から社会人まで幅広い方を対象」としていますが、準2級については平均的には高校生レベルの英語力が合格の目安となることを念頭に置いてください。
合格率および合格までの学習時間の目安
合格率
前述の通り公式な合格率データは現在公表されていませんが、2015年以前のデータによれば準2級全体の一次試験合格率はおおむね30%前後でした。
二次試験(面接)は合格者の約80%が通過しており、一次・二次トータルの最終合格率は概算で20%台後半(受験者の4人に1人ほど)と推定されます。
当時と比べ受験者の層や学習環境が変化しているものの、極端に易化・難化していないため現在も大きくは変わらないと考えられています。
重要なのはバランスよく点を積み上げる戦略と言えるでしょう。
必要な学習時間の目安
現在の英語力にもよりますが、よく言われる目安として「英検3級合格程度の力がある人が準2級に合格するには約30時間の追加学習」が必要とされています。
これは毎日1時間の勉強で約1ヶ月、毎日30分なら2ヶ月程度に相当します。
例えば中学卒業レベルの単語・文法は身についている状態から、プラス1000語程度の語彙習得と読解・リスニング練習、そしてライティング・面接対策にそのくらいの時間をかけるイメージです。
もちろん個人差がありますが、3級までの学習内容を土台に計画的に勉強すれば数ヶ月で十分狙えるでしょう。
もし現在のレベルが中学内容から大きく離れている場合はもう少し時間を見積もる必要があります。
まとめ
分析では、英検は級が上がるごとに必要学習量が大きく増加する傾向があり、特に準2級から2級への壁は厚いと指摘されています。
実際、5級~3級までは順調に1年おき程度でステップアップできても、準2級合格者が2級合格までに平均約2年かかるケースが多いというデータもあります。
このため、2025年度から準2級プラスが新設されましたが、まずは準2級に合格し基礎力を固めることが肝心です。
準2級合格は「高校中級レベルの英語力」を客観的に証明する資格でもあり、高校・大学受験や将来の資格活用にも繋がります。
合格率や必要勉強時間の目安も参考に、計画的な学習でぜひチャレンジしてみてください。
健闘をお祈りしています!