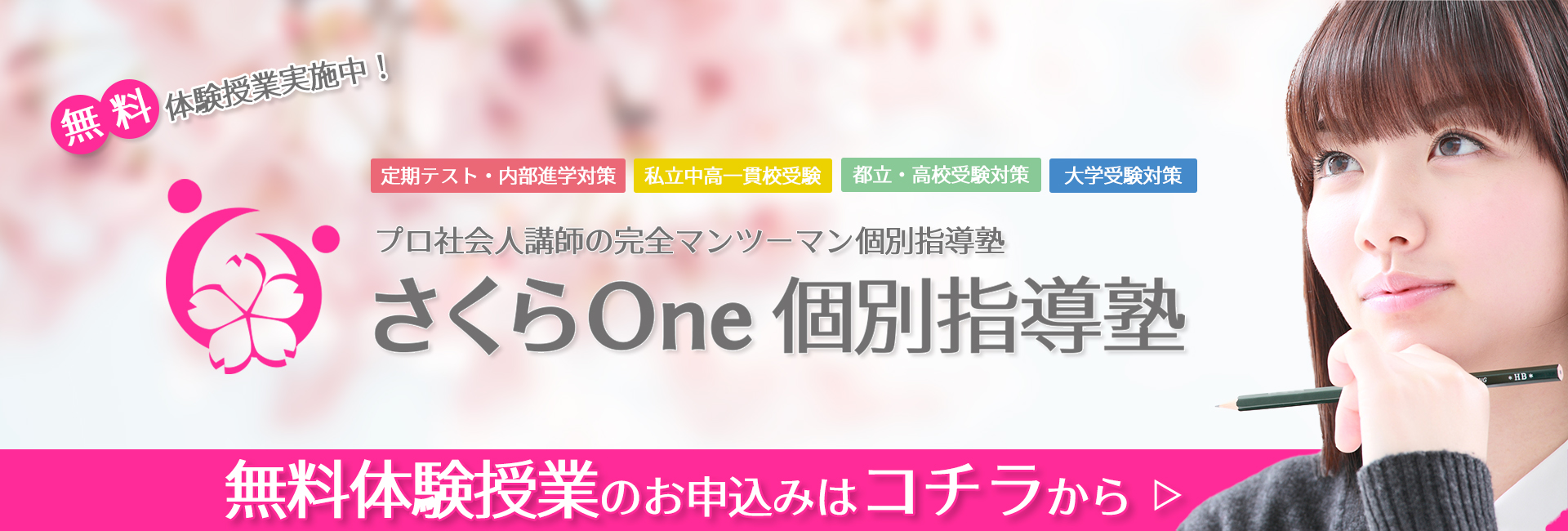【英検3級】合格するための完全解説ガイド

英検3級は、中学校卒業程度の英語力を測る試験で、多くの中学生が英語学習の一つの目標として受験します。
本記事では、英検3級の試験概要や最新の出題傾向、効果的な学習計画について解説します。
お子様の英語学習をサポートする保護者の皆様に向けて、丁寧に情報をお届けします。
英検3級の概要
英検3級は、5級・4級で培った基礎力の集大成に位置づけられる級で、レベルは中学卒業程度とされています。
日常的な話題について、基本的な語句で書かれた短い文章や会話の概要や要点を理解し、自分の考えや感想を理由を含めて簡単な英語で表現できることが求められます。
この3級からライティング(英作文)試験および面接形式のスピーキング試験が加わり、読む・聞くだけでなく書く力・話す力も評価されます。
試験は一次試験(筆記65分+リスニング約25分)と二次試験(スピーキング約5分)に分かれて実施されます。
受験の目安として、英検3級は学校英語で中学3年生レベル修了時に相当し、多くの中学卒業前後の生徒が挑戦します。
筆記試験の傾向
一次試験の筆記ではリーディング(読解)とライティング(英作文)の2技能が測定されます。
試験時間は65分で、この中で長文読解問題と英作文問題の両方に解答します。
近年の傾向として、出題内容は教科書レベルの語彙・文法を用いた身近な話題の文章や対話が中心で、文章量や難易度も中学英文法の範囲に収まっています。
筆記の出題構成はリーディングが大問3つ、ライティングが大問1つという内訳です。
それぞれの大問の内容は以下の通りです。
大問1(短文の語句空所補充)
文脈に合う適切な語句を選ぶ問題で、短文の空欄に入る単語を4つの選択肢から選択する問題が15問出題されます。
中学基本レベルの語彙や熟語が中心で、約5問程度は熟語の知識を問う内容です。
日頃から学校教材や英検用単語集を使って、語彙力・熟語力を着実に養うことが大切です。
大問2(会話文の文空所補充)
日常生活の場面を題材にした対話文が出題され、その中の空欄に当てはまる適切な文を選ぶ問題が5問あります。
会話の流れや意図を正しく理解し、最も自然なやり取りとなる選択肢を選ぶ力が求められます。
設問自体は短めですが、選択肢の文全体の意味を捉えて判断する必要があります。
大問3(長文の内容一致選択)
ある程度まとまった英文を読み、その内容に関する質問に答える読解問題が10問出題されます。
題材は「家庭」「学校生活」「天気」など身近な話題が中心です。
文章全体の主旨や登場人物の行動・考えを把握し、それと一致する内容を選択肢から選びます。
不明な単語があっても前後関係から意味を推測し、文章全体の大意をつかむ読解力がポイントになります。
ライティング(英作文)
与えられたトピックに対して自分の意見とその理由を述べる形式の英作文が出題されます。
25~35語程度の制限語数の中で、問に沿った内容を英文で書き表します。
例えば「あなたは朝食を毎日食べるべきだと思いますか。それはなぜですか。」といった問題が典型例です。
文法や語数が採点基準になりますが、合わせて意見と理由が的確に述べられているかという内容面も評価されます。
そのため、日頃から身近な話題について簡単な英文を書く練習を積んでおくことが重要です。
リスニング試験の傾向
一次試験のリスニングテストは約25分間で、大問が3部構成になっています。
放送される英語音声を聞き取り、設問に答える形式で、問題はすべて選択肢から解答を選ぶマークシート方式です。
大問によって音声が流れる回数が異なり、第1部は各問1回ずつ、第2部と第3部は各問2回ずつ音声が読まれます。
設問内容と各パートの特徴は以下の通りです。
第1部(会話の応答文選択)
短い対話を聞き、その最後の発言に対する最も適切な応答文を選ぶ問題が出題されます。
問われる応答は簡単な一文ですが、会話の流れを正確に聞き取り、相手の質問内容や発話の意図を的確に捉える力が求められます。
第1部の音声は全て各設問1回のみ流れるので、一度で要点を聞き取る集中力が必要です。
第2部(会話の内容理解)
もう少し長めの対話文を聞き、その内容についての質問に答える問題があります。
会話を最後まで聞いた上で、質問に対して正しい内容を述べた選択肢を選びます。
登場人物同士の関係や会話の目的・理由などを把握することがポイントとなります。
第2部の音声は各問2回ずつ放送されるので、1回目で大意をつかみ2回目で細部を確認するよう心がけましょう。
第3部(説明文の内容理解)
ナレーション形式の英文アナウンスやスピーチを聞き、その内容について問う問題が出題されます。
例えば「校内放送での連絡」「行事の案内」「簡単な物語」など、一人話しのまとまった英語を聞いて内容一致の選択肢を選びます。
要点となる日時・場所・数量などの情報を聞き逃さず、全体の趣旨を理解するリスニング力が試されます。
第3部の音声も各問2回放送されますので、落ち着いて聞き取っていきましょう。
リスニング問題全体を通して、題材は学校生活や日常会話など馴染みやすい内容ですが、話者の発言の言い換え表現が含まれる場合もあり表面的な単語だけで判断しない注意力が必要です。
対策として、過去問の音声スクリプトを読みながらディクテーション(書き取り)やオーバーラッピング(音声に合わせて音読)を行うと効果的です。
英文を聞き取る練習と同時に、自分でも発音する練習を積むことでリスニング力が向上します。
スピーキングテストの傾向
二次試験のスピーキングは英語による面接形式で、試験官と受験者が1対1で対面またはオンラインで実施します。
所要時間は約5分程度の短い面接です。
一次試験(筆記・リスニング)に合格した受験者のみが受ける試験で、内容は音読+Q&A形式となっています。
面接の当日は、試験官から「問題カード」と呼ばれる用紙が手渡されます。
カードには短い英語のパッセージ(文章)とイラストが印刷されています。
受験者はまずこのパッセージを黙読する時間が与えられ(約20秒)、その後、はっきりと音読するよう指示されます。
発音やイントネーションも評価に含まれますが、多少ゆっくりでも良いので落ち着いて正確に読み上げましょう。
音読の後、試験官との質疑応答(Q&A)が全部で5問行われます。
質問はNo.1~No.5まで順番に出されます。
No.1~No.3では、問題カード上のパッセージ内容やイラストに関する質問が出されます。
例えばパッセージの内容について「少年は最終的に何をしましたか?」と尋ねられたり、イラストの状況について「この絵の中で少女は何をしていますか?」と説明を求められたりします。
質問に答える際、パッセージやイラストに関するものは問題カードを見ながら回答して構いません。
実際、パッセージ中に答えの手がかりとなる情報が書かれている場合も多いので、落ち着いて英文を読み返しながら答えましょう。
なお質問No.3ではイラストの状況説明が課題となっており、この質問に答え終わると試験官から「カードを裏返してください」と指示されます。
以降の質問ではカードを見ずに答えることになります。
No.4・No.5では、カードを裏返した状態で試験官から受験者自身の意見や身近な経験に関する質問が2問出されます。
例えば「あなたは休日に家族と何をしますか?」や「あなたは〇〇が好きですか?」のような、受験者の生活や考えに関するシンプルな質問が想定されます。
これらはカードの文章に答えが書いてあるわけではないため、自分で英文で答える必要があります。
難しく感じるかもしれませんが、中学校で習う範囲の語彙・表現を使って簡単な英文で答えれば十分合格点が取れるレベルです。
質問が聞き取れなかった場合は一度だけ聞き返すことも可能です。
質問の意味は理解できたものの答え方に困ってしまった場合でも、黙り込んだり“I don’t know.”で諦めたりしないことが大切です。
質問文に出てきた単語を使ってでも一言何か答えようとする積極性が評価につながります。
たとえ完璧な文でなくても伝えようとする意志を見せ、最後まで英語で応答しましょう。
合格率と合格基準
合格率
英検3級の合格率は公開データによれば約50%前後です。
日本英語検定協会が2016年まで公表していた統計では、一次試験の合格率は2011~2015年の間ずっと50%を下回ることがなく、おおむね受験者の2人に1人が合格していたことが分かっています。
現在は正確な合格率は非公表ですが、試験内容が大きく変わっていないことから例年ほぼ半数程度が合格ラインを超えていると推定できます。
比較的合格しやすい級と思われがちですが、不合格になる受験者も多いため油断は禁物です。
合格基準
英検3級では合否判定に「CSEスコア」という統一スコア方式が用いられています。
一次試験(Reading・Listening・Writingの3技能合計)は1650点満点中1103点以上で合格、二次試験(Speaking)は550点満点中353点以上で合格となります。
各設問の配点は毎回の試験ごとに調整されるため「○問正解すれば合格」と一概には言えませんが、おおよそ全体の65~70%程度の得点率が合格ラインの目安とされています。
なお一次試験に合格すると二次試験の受験資格が与えられますが、最終的に二次試験も合格して初めて英検3級合格(合格証の交付)となります。
学習スケジュールと学習時間の目安
英検3級合格に必要な学習時間の目安は、現在の英語力によって大きく異なります。
英語初心者かどうかで15~200時間程度と幅があります。
例えば、既に中学3年レベルの学習内容を一通り理解している場合は、約15時間の対策でも合格可能とされています。
一方、基礎が未習得の場合や小学生から挑戦する場合は、100~200時間程度の時間を見込むとよいでしょう。
お子様の習熟度を踏まえて無理のない計画を立てることが重要です。
大切なのは、毎日の継続とバランスの良い学習(読む・聞く・書く・話すの4技能まんべんなく)です。
お子様のペースに合わせて無理のない計画を立て、途中で投げ出さず取り組めるようサポートしてあげてください。
まとめ
英検3級は英語初級者にとって大きな目標ですが、ポイントを押さえて対策すれば決して難し過ぎる試験ではありません。
お子様が合格に向けて努力している姿勢をぜひ肯定的に励まし、自信を持って本番に臨めるようサポートしてあげてください。
たとえ不合格だった場合でも、その過程で培った単語力や文法力、そして挑戦した経験は必ず次の学習につながります。
英語学習は継続が肝心ですので、合否に一喜一憂しすぎず今後の糧と捉える前向きさを持たせてあげましょう。
お子様の英検対策を家庭で進める中で、「何をどう勉強すればいいのか分からない」「苦手分野の克服方法が分からない」と不安に感じることもあるかもしれません。
そのような場合は、英検対策のプロに頼るのも一つの方法です。
さくらOne個別指導塾では英検3級を含む英語検定対策の指導を行っており、お子様の弱点やペースに合わせた個別カリキュラムで効率的に合格をサポートします。
ぜひプロの力を上手に利用しながら、お子様の英語力向上と英検合格を後押ししてあげてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
健闘をお祈りしています!