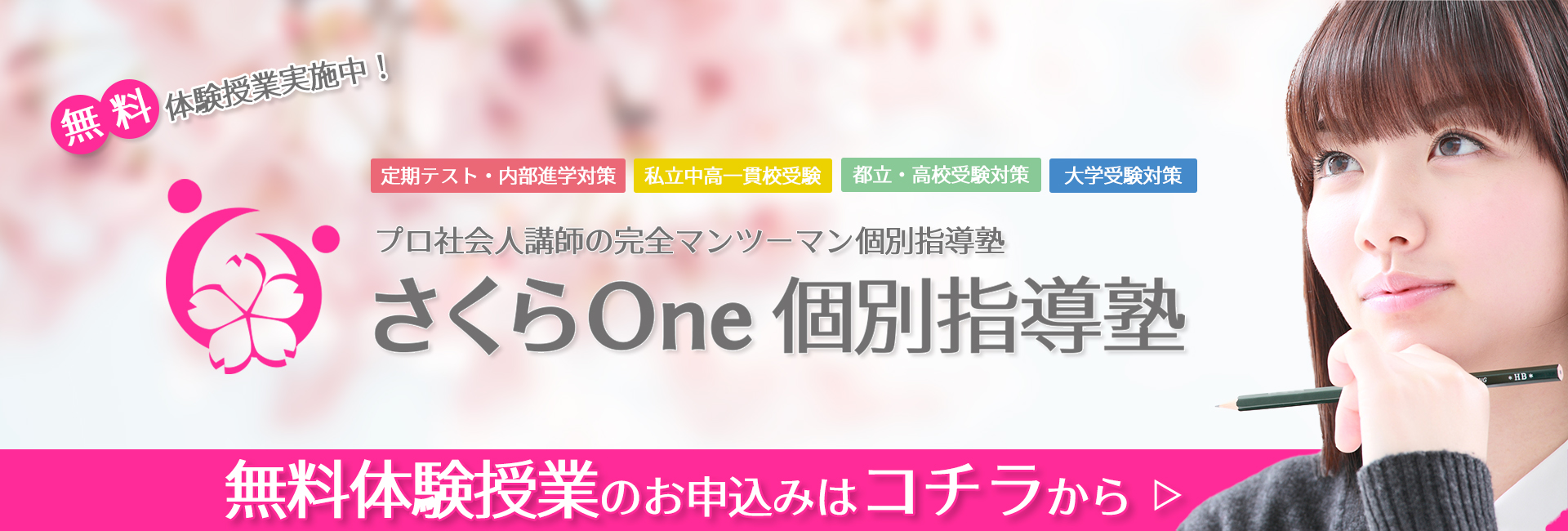【英検2級】合格するための完全解説ガイド

英検2級の受験を目指す方へ、出題傾向と効果的な対策情報をまとめました。
2024年度第1回検定から実施された出題形式のリニューアルを踏まえ、筆記・リスニング・スピーキング各セクションの変化や合格基準、そして学習計画の立て方まで詳しく解説します。
合格を目指すために、ぜひ最後までご一読ください。
英検2級の概要
英検2級は高校卒業程度の英語力が目安とされる級です。
日常生活や社会性のあるトピックについて、英語で文章を読みこなし自分の意見を述べられる実践的な力が求められます。
「読む・聞く・話す・書く」の4技能をバランスよく測定し、大学入試や就職でも評価される資格です。
想定される受験者層は、高校生が中心ですが、中学生で合格するケースもあり、社会人が自身の英語力証明として受験することもあります。
出題形式は2024年度に変更が加えられ、特にライティング問題が1題から2題に増加した点が大きな特徴です(後述)。
以下では、筆記(リーディング・ライティング)、リスニング、スピーキングそれぞれのセクションについて、最新傾向を詳しく見ていきます。
筆記試験(リーディング・ライティング)
英検2級一次試験の筆記(リーディング+ライティング)は試験時間85分で、出題形式のポイントは以下のとおりです。
リーディング
短文の語句空所補充(語彙・熟語)
短い文章の空所に文脈に合う適切な語句を補充する問題です。
4択の選択肢から選びます。
設問数は17問で、文法や慣用表現も含めた語彙力が試されます(従来より3問削減)。
文脈から前後関係を読み取り、適切な単語やイディオムを選ぶ力が求められます。
長文の語句空所補充
やや長めの説明文を読み、文中の空欄に入る適切な語句を補います。
設問数は6問で、文章全体の流れを理解しながら文脈に合う語(接続詞・副詞句など)を選ぶ読解力が必要です。
文章は社会・科学などの説明的な内容が扱われます。
長文の内容一致選択
内容把握問題です。
長めのパッセージ(Eメール形式の文面や一般的な説明文など)を読み、その内容に関する質問に答えます。
設問数は8問に調整されました(従来より4問削減)。
質問はパッセージ全体の主旨や詳細について問うもので、選択肢から最も適切なものを選びます。
題材は時事的な話題や身近な社会問題が多く、例えば環境、テクノロジー、教育、文化など多岐にわたります。
ライティング
リニューアル後の英検2級ライティングは2問構成です。
一つは英文要約問題、もう一つは従来型の意見論述問題となっています。
配点も高く、記述力が合否を左右する重要セクションです。
英文要約(要約問題)
新たに追加された問題で、与えられた英文(説明文など)を読み、その内容を3分の1程度の長さ(目安45~55語)で英語要約します。
ポイントは文章の主旨や各段落の要点を的確に掴み、具体的な表現を抽象的な表現に置き換え(パラフレーズ)しながら簡潔にまとめる力です。
解答は内容・構成・語彙・文法の4観点で評価され、それぞれ0~4点の段階評価(満点16点)で採点されます。
本文をそのまま書き写したり、自分の意見を書いてしまったりしないよう注意し、論理マーカー(howeverやDue toなど)を適切に使って要約を構成することが求められます。
初見の形式に戸惑わないよう、事前に公式サイト掲載のサンプル問題で練習しておくと良いでしょう。
意見論述(英作文)
従来から出題されている英作文問題です。
与えられたトピックについて自分の意見を英語で述べるもので、80~100語程度の 文章を書くことが求められます。
内容としては「賛成か反対か」を問う社会的なテーマが多く、過去問の出題例を挙げますと「環境にやさしい素材、オンライン会議、屋上緑化、ペット産業、新しいエネルギー、サプリメント」など、日常生活や社会問題に関する設問が頻出です。
受験者は自分の立場を明確にし、理由を2つ程度挙げて主張を展開します。
論理的な段落構成や適切な接続詞の使用、文法ミスの少なさが高得点の鍵です。
ライティングの傾向
2024年度の変更によりライティング問題が2問体制となったことで、時間配分と対策の重要性が増しました。
要約問題では的確に要点を掴む読解力と英語で簡潔にまとめる表現力が問われます。
一方、意見論述では自分の意見を論理立てて述べる力とトピックに関連する語彙が必要です。
日頃から英字新聞や時事トピックに触れて自分の意見を英語で書く練習をしておくと、面接対策にも繋がります。
採点基準を意識し、書いた英文は必ず見直して内容が問いに沿っているか、構成が論理的か、語彙・文法に誤りがないかをチェックする習慣をつけましょう。
リスニング試験の傾向
英検2級リスニングは約25分間で全30問が出題され、第1部と第2部の2セクションに分かれています。
音声はすべて1度だけ読まれる形式です。
問題文や選択肢の一部は冊子に印刷されていますが、読まれない情報も含まれるため先読みのスキルも重要になります。
各セクションの内容は以下のとおりです。
会話の内容一致選択
日常場面での対話(会話文)を聞き、その内容についての質問に答える問題が15問あります。
設問はほとんどがWhatで始まる質問で(Whyで始まるものも少数出題)、対話の中の具体的な意図や次の行動を問うものが多いです。
選択肢は問題冊子に印刷されており、4つの選択肢から最適な答えを選びます。
会話の場面はバラエティに富み、店員と客の会話、友人同士の会話、家族の会話、職場の同僚同士など多様です。
日常生活で起こりうるシチュエーションに関するリスニング力が試されるため、場面設定や登場人物の関係に注意しながら聴くことが大切です。
文の内容一致選択
一人話者のパッセージ(物語文・説明文)を聞き、その内容に関する質問に答える問題が15問あります。
こちらもWhatが主な設問ですが、WhyやHow、Whenなど理由や方法を問うものも含まれます。
場面の種類としては、個人の体験談やスピーチ、アナウンスなど公共的な放送、人文科学系の一般教養的な話題、自然科学系のトピックといった出題がされています。
選択肢は印刷されていない場合もあり、内容をしっかり理解していないと答えられないよう工夫されています。
ナレーションを聴き取る際は、話者の主張や事実関係を整理しながらメモを取ると効果的です。
リスニングの傾向
英検2級のリスニングは、準2級に比べ一文の長さや情報量がやや増加しますが、音声の読み上げスピード自体は準2級と大きく変わらないと言われています。
したがって、しっかり内容についていける集中力と、問われ方に慣れることが得点アップのポイントです。
過去問演習では必ず音声を1回だけ聴いて解答する練習をし、設問パターン(会話文なら次の行動を問う、物語文なら要点を問う等)を掴みましょう。
また、選択肢の先読みを行い、誰が何をしようとしているか・話のテーマは何かといった予測を立てて聴くと効果的です。
リスニング力強化には日常的に英語音声(ニュース・ドラマ・教材CD等)に触れ、英語を英語のまま理解する訓練を積むことが有効です。
スピーキングテスト(面接)の傾向
英検2級の二次試験は面接委員と1対1で行われるスピーキングテストです。
試験時間は約7分間で、与えられたカードの文章やイラストに基づいて受験者が解答します。
形式自体は従来から大きな変更はなく、2024年度リニューアルでも2級の面接形式に変更はありません(準1級のみ一部改善がありましたが、2級では従来通りです)。
面接の流れと各パートの内容は以下のとおりです。
音読
面接委員から渡される問題カードに英文パッセージ(約60語程度)が書かれており、まず最初にこのパッセージを黙読20秒の後、受験者は声に出して読み上げます。
発音やイントネーション、流暢さが見られますが、多少つかえても落ち着いて最後まで読むことが大切です。
質問1「パッセージ内容」
音読した英文の内容について理解度を問う質問が1つ出されます。
例えば「この文章は何について述べていますか?」など、パッセージ全体の主旨や一部内容の確認が主です。
パッセージを正しく理解していれば答えられる質問なので、音読時に内容をしっかり把握しておく必要があります。
質問2「イラスト描写」
カードに簡単なイラストが3コマ程度の連続した場面で描かれており、その展開を英語で説明するよう求められます。
例えば、ある人物が何かをしている3コマ漫画のような絵を見て、順番に「最初に~して、その後~し、最後に~した」と状況を説明します。
描写問題では適切な時制の使い分け(現在進行形や過去形など)や描写力が試されます。
面接委員は受験者の答えを途中で止めたりせず最後まで聞いてくれるので、細かいところまで自分の言葉で描写しましょう。
質問3,4「意見を問う質問」
最後に受験者自身の意見や考えを尋ねる質問が2問出されます。
内容はカードのトピックに直接関連しない一般的な事柄についてのものも含まれます。
日常生活や社会問題に絡めた問いが想定されます。
ここでは自分の考えを理由とともに英語で述べる力が重視されます。
質問に対し即答せず、一度 “Well, …” などと少し考える時間をとってから、理由を含めて答えると落ち着いて回答できます。
スピーキングの傾向
面接では内容(質問意図に合った答え)・発音・文法・語彙などが総合的に評価されます。
特にNo.3,4の意見問題は答えに正解がないため、自分の意見を具体的に述べることが求められます。
日頃から身近な話題(学校生活、テクノロジーの利点・欠点、国際交流の経験など)について自分の意見を英語で話す練習をしておくと、本番でも落ち着いて対応できます。
また、英検公式サイトの「バーチャル二次試験」などで模擬体験し、想定質問に対する回答を準備しておくと安心です。
面接官はフレンドリーに対応してくれますので、緊張しすぎず笑顔でコミュニケーションすることも大切です。
合格率と合格基準
英検2級の合格基準
合格基準はCSEスコアで定められており、一次試験と二次試験それぞれに基準点が設定されています。
具体的には一次試験(リーディング・リスニング・ライティング合計)1520点(満点1950点中)二次試験(スピーキング)460点(満点650点)を獲得することで合格となります。
一次・二次の両方で基準スコアを上回ることが必要で、トータルでは1980点(2600点満点)が合格ラインとなります。
各技能の満点は650点ずつに設定されており、換算上はリーディング・リスニング・ライティングで約6割強、スピーキングで7割強の正答率が目安です。
なお、高得点で合格した場合は「英検2級A」などと称され、留学用資格として活用できるケースもあります。
英検2級の合格率
英検協会は2016年以降公式に公表していませんが、過去のデータから推測される英検2級の平均合格率はおおよそ25%前後です。
実際、2011~2015年の英検2級合格率の平均は約25.58%と報告されています。
高校生のみで見ると2012年度の記録で参考にすると合格率は22.7%です。
同じく中学生は24.9%、小学生の合格率は42.4%でした。
年代別では中学生や小学生受験者の合格率が相対的に高いですが、これは英語に力を入れている層が受験しているためと分析されています。
いずれにせよ4人に1人が合格できるかどうかという難易度であり、決して簡単ではありません。
しかし裏を返せば、しっかりと対策を積めば十分に合格可能な試験とも言えます。
合格基準となるスコアは固定なので、過去問で自分の現在のスコアを把握し、足りない部分を補強する学習が重要です。
合格までに必要な学習時間の目安
英検2級合格に必要な勉強時間は現時点の英語力や学習環境によって大きく異なります。
一般的な目安として、高校で基礎的な英文法を習得している受験者なら約100時間、社会人で英語から遠ざかっている場合は150時間程度の学習が必要とも言われます。
一方、英語学習をゼロから始めて2級合格を目指す場合は、当然ながらさらに多くの時間を要します。
ある調査では0から準備して合格するには150~200時間(毎日1時間の勉強で約5~7か月)程度が必要との試算もあります。
まとめ
英検2級の最新傾向と対策を網羅しました。
リニューアル後は記述式問題が増え、より「使える英語力」が問われる方向にシフトしていますが、対策を積めば確実に実力アップに繋がります。
過去問演習と弱点克服の反復練習を重ね、自信を持って本番に臨んでください。
適切な学習計画のもとで努力を続ければ、きっと合格を手にできるはずです。
私たちさくらOne個別指導塾では、英検対策を含む英語の丁寧にサポートしています。
プロの講師が一人ひとりのペースに合わせたカリキュラムで指導しますので、英検が初めてでも安心です。
もし学習計画の立て方や勉強方法でお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
「英検2級合格」という目標達成に向け、教室一同全力で応援いたします。
それでは、皆様の健闘を祈ります!