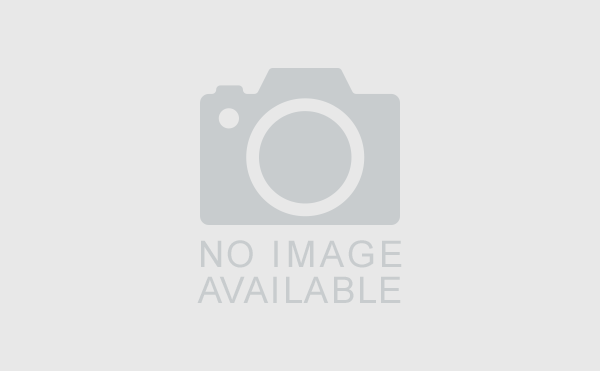高校と大学が連携する「高大連携」とは?
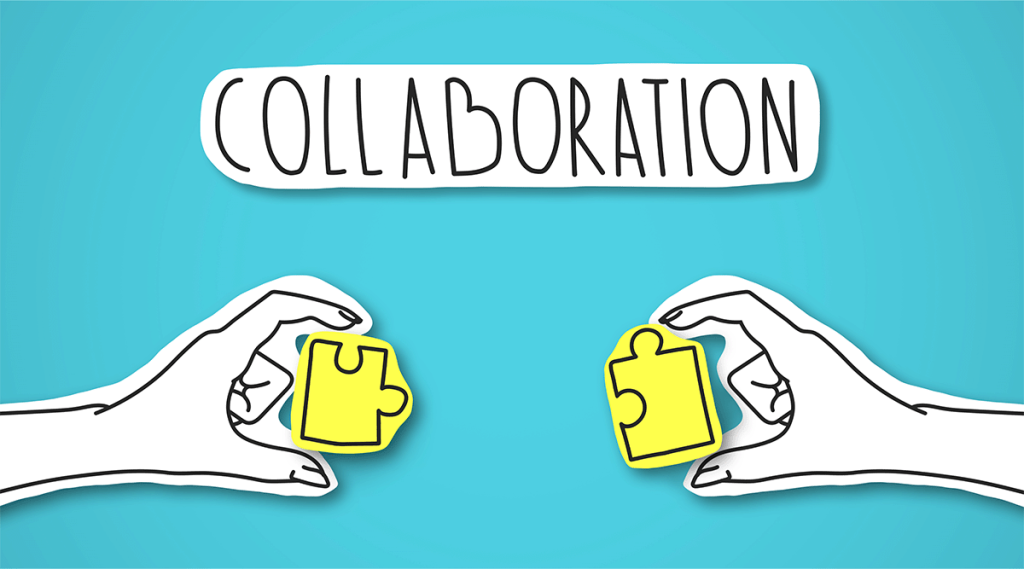
高校生のみなさん、大学の授業を高校生のうちから体験できたらどんな感じか想像したことがありますか?保護者の方々も、「高校と大学の連携」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。高校と大学がタッグを組んで高校生の学びをサポートする「高大連携」という取り組みがあります。今回は、その概要や目的、具体的な仕組み、メリットや課題、実際の事例、そして今後の展望について、解説します。
高大連携の概要
高校と大学が協力して高校生の力を伸ばす取り組み
高大連携とは、その名のとおり高校と大学が連携して行う教育プログラムのことです。具体的には、高校と大学が協力することで、高校生が大学レベルの授業や研究に触れられる機会を作り出す取り組みを指します。例えば、大学の授業を高校生が特別に受講したり、大学の先生が高校で特別講義を行ったりすることなどが含まれます。高校生にとってみれば、「大学生になる前に大学の勉強を先取り体験できる」仕組みと言えるでしょう。
高大連携は、1990年代後半から日本で徐々に制度化・推進されてきました。平成10年度(1998年)からは、高校生が大学等で受けた科目等履修生や聴講生としての学習成果、公開講座での学習成果などを高校の単位に認定できる制度が導入されました。これは、高校生が学校の外で大学の勉強にチャレンジした成果を、高校の卒業に必要な単位として認めてもらえるということです。こうした制度も後押しとなり、現在では全国各地で様々な形の高大連携プログラムが行われており、徐々に広がりを見せています。
高大連携の目的
一人ひとりの個性・能力を伸ばすために
なぜ高校と大学が連携して高校生に大学レベルの学びを提供するのでしょうか?その大きな目的は、高校生一人ひとりの持つ多様な能力・個性を効果的に伸ばすことにあります。
現代の高校生は興味関心や得意分野が実に様々です。中には「この分野をもっと深く学びたい!」「高校の勉強だけじゃ物足りない…」という強い意欲を持つ生徒もいるでしょう。高大連携は、そうした特定分野で高い能力や強い学習意欲を持つ高校生に、早いうちから大学レベルの高度な教育研究に触れる機会を与えることを目指しています。例えば、科学が大好きで高校の範囲を超えた実験に挑戦したい生徒に、大学の研究室で実験を経験してみる、といったことも可能になります。
また、高大連携には高校から大学へのスムーズな接続を実現するという狙いもあります。高校と大学の接続というと、多くの場合「大学入試」がクローズアップされがちですが、入試のみに偏らず、学びの面で高校と大学を滑らかにつなぐ有効な手段と位置付けられています。高校在学中に大学の学びを経験することで、大学進学後のギャップを減らし、スムーズに大学での勉強に入っていける効果も期待されています。
高大連携の目的は「高校生が持つ才能や興味を高校〜大学という枠を超えて伸ばすこと」と「高校教育と大学教育の橋渡しをして円滑な接続を図ること」にあると言えます。
高大連携の仕組み
どんな連携が行われているの?
高大連携と言っても、連携方法は様々です。高校と大学が協力して行うプログラムにはいくつかのタイプがあります。主な取り組み例を以下にまとめました。
| 連携の形態 | 内容(高校生への提供内容) |
|---|---|
| 大学の科目等履修生として授業を受講 | 高校生が大学の授業科目を正式に履修し、試験に合格すれば大学の単位を取得できる制度。取得した単位は高校卒業後、大学側で認定される場合もあります。 |
| 大学の聴講生として授業を受講 | 高校生が大学の授業を聴講生(講義を聞くだけの受講生)として受講する制度。単位は取得できませんが、大学の学びを体験できます。 |
| 大学の公開講座を受講 | 大学が一般向けに開放している公開講座に高校生が参加する形態。高校生でも受講可能な内容で、興味分野の学びを深められます。 |
| 大学教員による出前授業・特別講義 | 大学の先生が高校に出向いて実施する特別授業。例えば「出前講座」や土曜日に行う特別講義など。大学レベルの授業を高校で直接受けられます。 |
| 先進的プログラムでの連携(SSHやSPP等) | 国の指定するスーパーサイエンスハイスクール(SSH)やサイエンス・パートナーシップ・プロジェクト(SPP)等における、高校と大学・研究機関の協働プログラム。高度な科学研究や語学研修などを高校生に提供。 |
| インターネットや衛星通信を活用した授業 | インターネット配信や衛星通信を使って、大学の授業を遠隔地の高校生に届ける形態。近くに大学がない地域の高校生でも参加できます。 |
このように、高大連携の仕組みには高校生が大学に行って学ぶタイプと、大学の先生や授業が高校に来るタイプがあります。科目等履修生として大学の授業に参加するケースでは、成績評価も大学生と同じように行われ、合格すれば大学の単位を先取り取得できる点が特徴です。一方、聴講生や公開講座の場合は単位認定はありませんが、気軽に大学の学問に触れられるメリットがあります。また、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)では指定校の高校生が大学や研究機関と連携して本格的な研究活動に挑戦できますし、遠隔授業なら自宅や高校で全国の大学の講義を受けることも可能です。
高校によっては、こうした高大連携プログラムで得た学習成果を高校の単位として認定してくれる場合もあります。例えば、大学の公開講座を受講して修了証をもらったら高校の選択科目の単位にカウントする、といった具合です。各高校の裁量で認められるものですが、学校外での学習成果も正式に評価してもらえるのは嬉しいですね。
高大連携のメリット
高校生・高校・大学それぞれにプラス効果
高大連携には、参加する高校生本人にとって大きなメリットがあるのはもちろんですが、実は高校側・大学側にも様々な効果や利点があります。
高校生にとってのメリット
①学習意欲・目的意識の向上
大学の授業を体験することで、「もっと学びたい!」という意欲が湧いたり、自分の進路目標が明確になったりします。普段の高校の授業だけでは味わえない高度な内容や最先端の研究に触れることで、学ぶことの面白さを再発見する生徒もいます。「大学ってこんなことを勉強するのか!」と早い段階で知ることで、将来の進学に向けたモチベーションアップにもつながります。短期間の体験でも、大学の模擬授業を受けることで進路への目的意識が高まるという報告もあります。
②大学進学後のスムーズな適応
あらかじめ大学レベルの学習に触れておくことで、大学入学後の勉強のスタイルに慣れやすくなります。高校と大学の「学びのギャップ」を埋め、1年生の最初からスムーズに授業についていけるという効果が期待できます。
③得意分野の伸長
自分の得意な分野や興味のある分野を高校の枠を超えて追求できるため、その分野での才能をさらに伸ばすことができます。例えば、高校では習わない専門的な実験や高度な内容を学ぶことで、将来の専門分野への準備にもなります。
高校側のメリット
①指導力の向上・進路指導の充実
高校の先生にとっても、大学の最新の教育内容や教授法に触れることは刺激になります。大学の先生との交流や連携を通じて、高校教員自身が研修を受けるような効果もあります。その結果、大学の教育内容を踏まえた進路指導ができたり、高校の授業改善につながったりと、学校全体の教育力アップが期待できます。
②特色ある教育プログラムの展開
高大連携を取り入れることで、他校にはない特色ある教育プログラムを実施できます。例えば、近隣の大学と組んで特別講座を開いたり、SSHに指定されて大学と共同研究を行ったりすることで、学校の魅力づくりにもつながります。地域の大学と連携している高校は、地域社会に開かれた学校として評価されることもあります。
大学側のメリット
①優秀な学生の発掘と育成
大学にとっては、高校生のうちから自大学の専門科目に触れてもらうことで、その分野に関心の高い優秀な学生を早い段階から発掘できます。科目等履修生として受け入れた高校生が、そのまま将来自大学に進学してくれるケースもあります。
②教育効果の地域への還元
大学が高大連携に取り組むことは、大学の社会貢献にもなります。大学が持つ教育資源や最先端の研究成果を地域の高校生に還元することで、地域社会への貢献を果たすことができます。昨今、大学には地域や社会への貢献が求められていますが、高大連携はまさにその一環と言えるでしょう。
③大学教員にとっての研修機会
逆に大学の先生にとっても、高校生に教えることで高校までの教育内容や学生の実情を知る機会となり、教育方法を見直すきっかけになります。高校生に平易に教える工夫をすることで、自身の教授スキル向上にもつながるでしょう。
このように、高大連携は 高校生本人だけでなく、高校・大学双方に教育的な効果 をもたらす点が大きなメリットです。高校生に大学体験を提供することが、結果的に高校教育と大学教育の双方を活性化する好循環が生まれるのです。
高大連携の課題
乗り越えるべき壁とは?
良いことづくめに思える高大連携ですが、実際に運用するにはいくつかの課題や難しさも指摘されています。ここでは主な課題と、その対策・工夫について解説します。
①時間割や日程の調整
高校生は通常、平日は高校の授業がびっしり詰まっています。その中で大学の授業に参加したり特別プログラムに取り組む時間を確保するのは簡単ではありません。高校生の学習負担に配慮したスケジュール調整が必要です。例えば、学校外学習扱いとして長期休み(夏休み等)や土曜日を活用した集中講義の形で実施する工夫が行われています。実際、夏休みに大学のサマースクールとして高校生向け講座を開く大学もあります。また、中高一貫校では6年間を柔軟に使えるため、高校2・3年次に大学連携の授業を組み込む、といった編成も可能です。このように、高校生が無理なく参加できる時間帯・期間を選ぶことが重要です。
②地理的な距離の問題
高校の所在地によっては、「近くに大学がない」「通学圏に大学がない」という場合もあります。地方の高校生にとって、物理的な距離は大きなハンデになりえます。しかし近年は、インターネットや衛星通信を活用した遠隔授業によって距離の壁を乗り越える試みが増えています。例えば、自宅にいながら有名大学のオンライン講義をライブ受講するといったことも可能になってきました。ただし遠隔授業では双方向性やフォロー体制が不十分になりがちです。そのため、リアルタイムで質問できる仕組みや高校側でのサポート教員配置など、生徒の学習意欲を維持する工夫が必要とされています。技術の力で地理的制約はかなり解消できますが、人間的なサポートも欠かせません。
③経費・コストの負担
高大連携のプログラムを実施するには、追加の経費も発生します。例えば、大学側が高校生向けに教材を準備したり、人件費をかけて特別講義を行ったり、高校側も生徒を引率したりといったコストです。これらをすべて参加者や学校の自己負担にしてしまうと、継続が難しくなります。現在、国も含めて高大連携への財政支援が検討・実施されています。文部科学省では特色ある教育連携には補助金(たとえば「特色GP」「現代GP」などのプログラム)が申請により支援される仕組みも整えています。限られた予算の中で継続的に取り組むには、既存のインフラ(高校のネット環境や地域の教育ネットワーク)を活用するなど創意工夫も求められます。今後さらに公的支援を充実させることが課題と言えるでしょう。
④高校・大学教員の相互理解と協力体制
高大連携を成功させる鍵の一つは、高校の先生と大学の先生がどれだけ協力できるかです。現状では「高校の先生は大学教育の実情を十分に知らず、大学の先生も高校教育をあまり理解していない」という指摘があります。お互いの教育現場に対する理解不足があると、連携の意義も共有しづらくなってしまいます。そこで各地で高大連携協議会など高校・大学間のネットワーク作りが進められています。単に会議体を作るだけでなく、何を高校生向け連携授業として提供するかを一緒に企画立案するなど、実質的な協働関係を築くことが大事です。また、高校教員向けの研修に大学教員が参加したり、逆に大学教員向けFD研修に高校教員が参加したりして情報交換する取り組みも有効だとされています。教師同士の交流が進めば、「高校で今こういう指導をしています」「大学では最近こういう教育改革があります」など相互理解が深まり、連携プログラムの質も向上するでしょう。
⑤対象となる生徒の選抜・支援
高大連携は「高校生なら誰もが参加できる」ものではなく、主に高い意欲・能力を持つ生徒に焦点を当てたプログラムです。そのため、場合によっては 参加生徒の選抜や絞り込み が必要になることもあります。たとえば大学の科目等履修生として受け入れる場合、内容についていけるだけの学力があるか事前に審査するといったことも考えられます。一律に全員参加では本来の目的を達成しにくいため、適性のある生徒に責任を持って機会を提供することが重要です。選抜された生徒には、その後高校側でフォローアップ(事後指導やメンターによる相談対応など)を行い、不安や学習上の課題をケアする体制も求められます。
以上のような課題はありますが、どれも工夫次第で乗り越え可能なものです。高校と大学、そして行政や地域が協力し合い、知恵を絞ってこれらの壁を少しずつクリアしていくことで、高大連携はより充実したものになっていくでしょう。
高大連携の具体的な事例紹介
実際にどのような高大連携の取り組みが行われているのか、いくつか具体例を見てみましょう。ここでは代表的な事例をピックアップして紹介します。
東京工業大学「衛星通信による全国高校遠隔授業プロジェクト」
東京工業大学では平成14年度(2002年)より、衛星通信を利用して大学の授業を全国の高校に配信する高大連携プロジェクトを開始しました。大学で実際に行われている学部の講義(例えば「化学」「認知科学」「生物学」などの基礎科目)を衛星回線経由で高校の教室にライブ配信し、希望する高校生が視聴・受講できる仕組みです。参加した高校生には公開講座の受講証明書が発行され、学習の成果として記録に残る工夫もされています。このプロジェクトにより、近くに大学がない地方の高校生でも高度な内容の授業を受ける機会が提供され、受講者には学習成果として公開講座受講証明書を交付するなどの工夫を行っています。
岡山理科大学「インターネット遠隔授業による高大連携」
岡山理科大学では、インターネットを活用した遠隔授業で高校生に大学の専門科目を提供する取り組みを行っています。情報科学科の開講科目である「インターネット入門」「アルゴリズム入門」(各1単位)をオンラインで高校と結んで配信し、所定の成績を収めた高校生には大学の単位を認定する制度です。高校生は自宅や学校でネット経由の講義を受け、大学の先生の指導のもとレポート提出やテスト受験を行います。優秀な成績を取れば大学入学後にその単位が認められるため、在学中に大学の単位を先取りできる点が特徴です。このようにITを駆使することで、物理的な距離を超えて大学レベルの学びを提供する先駆的事例と言えるでしょう。
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)における大学連携
文部科学省が指定するスーパーサイエンスハイスクール(SSH)では、科学技術人材の育成を目的に高校と大学・研究機関が連携した教育プログラムが展開されています。SSH指定校の高校生は、大学の研究室に出向いて最先端の研究に触れたり、大学教授による特別講義や実験指導を受けたりします。例えば、あるSSH校では地元の大学と協力して科学研究プロジェクトを立ち上げ、高校生が大学生や大学院生とチームを組んで研究発表を行うといった活動も報告されています。また、サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト(SPP)では高校・大学・科学館などが連携し、天文学や生物学など専門テーマの講座や合宿研修が行われています。これらの事例は、高校の授業ではできない本格的な体験を大学の力を借りて実現している好例と言えるでしょう。
上記のほかにも、各地域で特色ある高大連携が進められています。複数の高校と複数の大学が連携して、交流イベントや合同授業を開催するケースや、企業・自治体も交えた三者連携でキャリア教育プログラムを実施する例など、その形は実に様々です。興味がある人は自分の地域や志望大学でどんな取り組みがあるか調べてみると面白いでしょう。
高大連携の今後の展望
さらに広がる学びの可能性
最後に、高大連携の未来について展望してみましょう。高大連携は今後ますます重要性を増すと考えられています。その背景には、高校生の興味・関心の多様化や、高校教育と大学教育の接続を滑らかにしたいという社会的な要請があります。では、具体的にどのような方向に発展していくのでしょうか。
高大連携プログラムの一層の拡大と定着
現在は一部の意欲ある高校や大学が中心となって進めている高大連携ですが、将来的にはより多くの学校で当たり前のように実施されることが期待されています。文部科学省でも、高校・大学それぞれの教育目的との調和を図りつつ、各高校生の能力や適性に応じて高大連携の取組を更に拡大していく必要があるとしています。具体的には、今まで参加機会が少なかった地域や普通科高校にも広げたり、文系理系問わず様々な分野で連携プログラムを提供したりといった形で、すべての意欲ある高校生にチャンスが行き渡るような環境づくりが目指されるでしょう。
大学入試改革との一体的な推進
高大連携は、いわば大学入学前の教育接続を円滑にする取り組みですが、日本全体では高大接続改革として大学入試制度の見直しも進んでいます。例えば、思考力や表現力を重視した新テスト(大学入学共通テスト)の導入や、入試での学びのポートフォリオ活用など、高校と大学の接続をスムーズにする政策が打ち出されています。こうした入試改革と連動して、高大連携の意義も再評価されています。入試偏重ではない多面的な接続を実現する一つの手段として、高大連携がますます活用されていくでしょう。
単位互換や学習成果の活用の柔軟化
将来的なアイデアとして、高校生のうちに大学で取った単位を、進学先の大学で認定できるようにする取り組みも考えられています。これは、アメリカで行われている「アドバンスト・プレイスメント(AP)」という仕組みにヒントを得た発想です。APでは高校在学中に大学レベルの科目を履修し、試験に合格すれば大学の単位として認められます。日本でも、ある大学で高校生が取得した単位を他大学に進学した際にも認定できるように大学間協定を結ぶ動きが広がれば、より一層高校生の学習意欲を刺激するインセンティブとなるでしょう。現時点では各大学ごとの対応ですが、将来的には制度的な整備も含めて柔軟な単位互換が検討される可能性があります。
高校・大学・社会の三者連携へ
高大連携は、高校と大学の協力が中心ですが、今後は地域社会や産業界を巻き込んだ連携へと発展していくかもしれません。すでに大学の社会貢献の一環として高大連携が注目されていますが、例えば地元企業と大学・高校が一緒になって課題研究に取り組む、地方自治体が窓口となって複数高校と大学をマッチングするといった広がりも考えられます。教育委員会など公的機関も、高大連携が一部の学校だけで終わらず地域全体に広がるよう調整役となることが期待されています。
このように、高大連携はこれからも形を変えながら発展していくでしょう。ポイントは、「高校生一人ひとりの可能性を伸ばす」という原点です。それを実現するために、高校という枠、大学という枠にとらわれず、柔軟に教育の場をつなげていく発想が求められています。【高校生と大学生という区分に過度にとらわれず、本人の能力・適性に応じた学びの場を提供する】――高大連携の取り組みは、これからの教育の在り方を先取りするものとも言えます。
希望の進路を目指すために
高校生のみなさんも、「自分もやってみたい!」と思える高大連携プログラムがあれば、ぜひ積極的にチャレンジしてみてください。大学生や大学の先生と触れ合う中で、新たな発見や将来の夢が見えてくるかもしれません。保護者の方も、お子さんの興味や適性に合った連携プログラムがあれば、後押ししてあげてください。高大連携は、高校と大学が協力して未来の可能性を広げる、ワクワクするような取り組みなのです。
高大連携対策ができる塾選びにお困りの際は、対策に向けたマンツーマン指導を行っている、さくらOne個別指導塾へお気軽にご相談ください。
学校別の傾向や必要な学習方法も熟知しております。もちろんお子さま一人ひとりで異なる対策も必要になるため、現状や個性に合わせた指導をいたします。
成功率を高めるためには高大連携の特色を知り、お子様自身にあった学習方法で対策を取っていかなければなりません。高大連携を目指す方は、一度、無料体験授業も行っている弊社さくらOne個別指導塾をご検討下さい。
参考文献:文部科学省(高等学校と大学との接続における一人一人の能力を伸ばすための連携(高大連携)の在り方について)
文部科学省「大学への早期入学及び高等学校・大学間の接続の改善に関する協議会」報告書(平成19年)